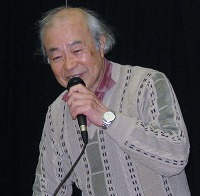ミサ
ミサはキリストのいけにえの継続でありキリストの聖体聖血を司祭の手をもって聖父に捧げる儀式である。ミサに連なる信者もただミサを拝聴するのではなくて、そこに参加する。司祭の手を通してばかりではなく、信者も司祭とともに汚れなき いけにえ を奉献して自分自身を神に捧げる。式次第は、
- 入祭の儀 入堂、入堂唱、祭壇のもとでする祈り、登壇、哀れみの賛歌(キリエ)、栄光の賛歌(グロリア)、入祭祈願
- ことばの祭儀 聖書朗読、福音の朗読、説教、信仰宣言(クレド)、共同祈願
- 聖体祭儀 奉納の儀、奉納唱、奉納祈願、叙唱、感謝の賛歌(サンクトゥス)、典文
- 聖体拝領の儀 主の祈り、平和の賛歌(アニュス・デイ)、聖体拝領、聖体拝領唱、聖体拝領祈願、閉祭の儀
の4部よりなる。カトリックの盛儀ミサには
- 読唱ミサ misa lectaと
- 歌唱ミサ misa in cantu
がある。歌唱ミサには、助祭(司祭に次ぐ聖職者)及び副助祭を伴って行われる
(2-1) 歌ミサ misa cantataと
(2-2) 盛儀ミサmisa solemnis、
助祭のみ伴う歌唱ミサ misa in cantu cum solo diaconoがある。
ミサ聖祭の歌
- 入祭唱 Introitus
- 哀れみの賛歌KIRIE
- 栄光の賛歌GLORIA
- 聖書朗読後の典礼賛歌 Graduale その他
- 信仰宣言CREDO
- 奉納唱 Antiphona ad Offertorium
- 叙唱 Proefatio
- 感謝の賛歌 SANCTUS、BENEDICTUS
- 主の祈り Pater noster
- 平和の賛歌 AGNUS DEI
- 聖体拝領唱 Antiphona ad Communionem
が主要なものである。太字の部分が、ミサ通常文、下線部分がミサ固有文である。
ミサ曲
ミサ式文のうち、通常文のなかで参列信徒またはその代表である聖歌隊が歌唱することにさだめてある部分の大部分を一括作曲した曲をミサ曲という。音楽的形態は
(1) 合唱、独唱、大管弦楽伴奏を用い、式文の各段を細切し、各曲異なった曲態に作曲したmisa solemnis (highmass, Hochamt, grand-messe)
(2) 無伴奏あるいは人声を楽器音で重ねて伴奏し、あるいはオルガンで通奏低音を奏する合唱曲態のもので、原則として式文・各段落を細分しないmisa brevisがある。無伴奏六部合唱の《教王マルチェリスのミサ》(パレストリーナ)はその代表例でローマカトリック教会音楽の典型とされる。
以上の曲態を用いずミサを挙行する場合はグレゴリオ旋律を歌唱する。オルガンにグレゴリオ旋律を用いた曲を奏させ、人の読唱と交互に、あるいはオルガン曲だけを奏させることもある(オルガンミサ曲)。
レクイエム
冒頭の入祭唱が、requiem(《休息を》の意味)で始まるのはレクイエム・ミサと呼ばれている。典礼祭では
- 入祭唱 Introitus
- あわれみの賛歌 キリエ Kyrie
- 昇階唱 グラドゥアレ
- 詠唱 トラクトゥス
- 続唱 セクエンツィア Sequenz
- 奉納唱 オッフェントリウム Offentorium
- 感謝の賛歌 サンクトゥス Sanctus
ベネディクトゥスBenedictus
- 平和の賛歌 アニュス・デイ Agnus Dei
- 聖体拝領唱 コンムニオ Communio
が歌われるが、レクイエム曲として一連の作曲がされるのはそのうちミサ通常文たる、キリエ、サンクトゥス、アニュス・デイの他ミサ固有文の何曲かであるのが普通である。絶唱はディエス・イレー(Dies irae 怒りの日)であり、歌詞は1200年頃、旋律は1300年頃に遡りうる。
以上の解説は平凡社 世界大百科事典及び音楽の友社 標準音楽辞典からの抜粋です。
Missa Solemnisの作曲家
Beethovenの他に、Solemnisを冠したMissa曲を書いている作曲家。
1. Liszt, Ferenc /Jqnos Ferencsik, Budqpest Symphony Orchestra, Chorus of the Hungarian Radio and Television
2. Weber, Carl Maris von /Ernst Ehret, Chor und Orchester von St Michael, München
3. Berlioz, Louis Hector/ John Eliot Gardiner, Orchestre Revolutionnaire et Romantique, Monteverdi Choir
Beethoven のMissa Solemnisをきく
一般的にはSanctus とBenedictusは別の楽曲として構成されるが、ベートーベンの荘厳ミサ曲では、Sanctus とBenedictusは統一された楽曲として続けて演奏される。ここでは、各部の出始めをArturo Toscaniniの演奏でお聴きいただきます。
KIRIE, GLORIA, CREDO, SANCTUS and BENEDICTUS, AGNUS DEI
Benedictusでは独奏ヴァイオリンが美しい。
SANCTUS Günter Wand/ Chöurs et Orchestre du Gürzenich de Cologne
SANCTUS Karl Böhm/ Berliner Philharmoniker, Chor der St. Hedwigs-Kathedrale
SANCTUS Georg Solti/ Chicago Symphony Orchestra & Chor
SANCTUS Herbert von Karayan/ Berliner Philharmoniker & Wiener Singverein
SANCTUS Otto Klemperer/ New Philharmonia and Chorus
SANCTUS Eugen Johum/ Concertgebouw Orchestra, Amsterdam & Netherlands Radio Chorus
SANCTUS Kurt Masur/ Rundfunktchor und Gewandhausorchester Leipzig
音源は、Masurのreel-to-reelを除いてLPです。Toscaniniと Wandに対してPioneer PL-L5とDENON DL-103LCiiを使用し,その他の演奏者に対してはELP Laser Turntableを使用し、TASCAM DA-3000 DSF 5.6MHzにて録音しました。MasurはAKAI GX-635Dで再生します。
キリスト教信者ではない私が宗教音楽を聞く
キリスト教信者でない人は、宗教音楽を聴くことに抵抗を感じるという。あるいはキリスト教徒でなければ宗教音楽を真に理解することは出来ないといわれる。人間は傷病老死の身体の患い、喜怒哀楽―落胆、失望、怨恨、悔恨、嫉妬、羨望、欲望、希望、願望、妄想、期待、恐怖、不安など―の心の煩いに常に苛まれており、その内実は地域、時代、社会的階級、性別、宗教等等によって異なるであろう。これらを超越した自然への畏敬、あるいは世界を支配する超自然的な何物かの存在を感じ期待したくなるのは人間誰しも共通するものであろう。その時頼るべき哲学が宗教であり、いわゆる宗教音楽と呼ばれるものは、多かれ少なかれキリスト教を信仰する作曲家に依るものであるというだけである。
宗教に対するフィルターを取り払えば、キリスト教信者でなくても感じるものがある。ラテン語を勉強して言葉の意味を理解しようとするのは止めよう。疑念が生じるし、どうせすぐに忘れてしまうから。低音の響きが物足りないとか、高音が出ていないとか、雑音が多いなどと音を聴くことを止めよう。何を言おうとしているのか考えるのを止めよう。肩の力を抜いて、眼を閉じよう。空気の振動は私の記憶のなかに、あるいは大きく露出し、あるいはほとんど埋もれて沈潜し、あるいは澱んでいるいる何かに触れる。ささやかな共鳴が、やがて私の脳を揺さぶり覚醒させる。
以上