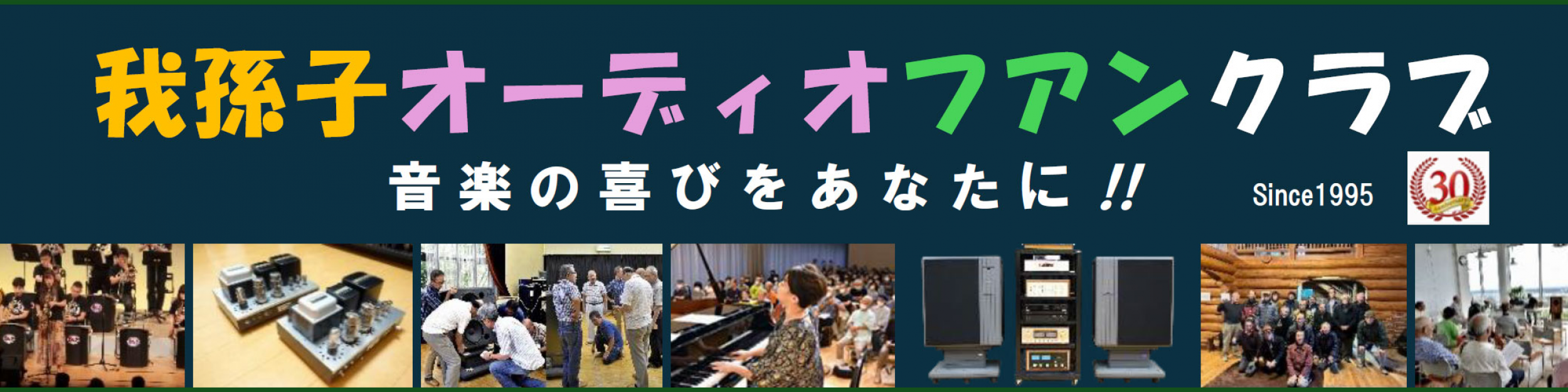AAFC例会資料 2022年8月28日
大久保貴枝子
オーボエとクラリネット


オーボエの吹き口 オーボエのベル クラリネットの吹き口 クラリネットのベル




●オーボエの特徴は優しく甘美でどこか哀愁漂う音色にあります。管楽器の中で始めてオーケストラに採用されたのはオーボエだそうです。当時の人々もその音色の良さに引き込まれたからでしょう。その音色や表現力の豊かさから、オーケストラではソロを担当する事が多い楽器です。魅力的な楽器である反面、オーボエは「世界一難しい木管楽器」として知られています。環境に影響されやすい楽器である事と、リードとの相性はオーボエ奏者として一生苦しめられるものです。
●循環呼吸は、呼吸の間も絶え間なく口から空気を吐き出すことによって息継ぎの無音時間をなくす演奏技法。鼻で吸っている間は、頬または喉に溜めておいた空気を吐き出すことで吐息を持続させます。長い音符や呼吸タイミングの困難なフレーズも一息で演奏できます。
①カール・ライスター「クラシック・クラリネット」より ソナタ ト短調 作品29
Fリース作曲(1784~1838)
カール・ライスター(CL.) フェレンツ・ボーグナー(P)
②ハインツ・ホリガー オーボエ協奏曲 ト短調
Ⅰアレグロ Ⅱアダージオ Ⅲロンドアレグロ
ルブラン作曲(1752~1790)
③藤家虹二 「ELEGIE」より
・エレジー
・ビー クワイアット ベイビー ・クラリネットの子守うた
【演奏者プロフィール】
- 「ザ・キング・オブ・クラリネット」 カール・ライスター

ライスターは1937年にドイツで生まれ、最初の音楽のレッスンを、クラリネット奏者だった父から受けた。1953年から56年にかけてベルリン音楽大学で学び、1957年に19歳でベルリン・コーミッシェ・オーパーのソロ・クラリネット奏者となる。
1959年にヘルベルト・フォン・カラヤンの指揮するベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のソロ・クラリネット奏者に就任。同時に、ソリストや室内楽奏者としての活動も始める。またライスターは、国内外のコンクールで数多くの賞を受けている。ドイツ・グラモフォン、EMI、フィリップス、テルデック/ワーナー、オルフェオ、MDG、BIS、Nimbus、ソニー、カメラータ・トウキョウなどのレーベルにクラリネットのレパートリーのほぼ全てにわたる録音を残している。
- ハインツ・ホリガー オーボエ奏者、指揮者、作曲家。現代の最も多才で非凡な音楽家。1939年、スイス・ランゲンタールに生まれる。

1959年ジュネーヴ、1961年ミュンヘンの両国際音楽コンクールで優勝し、オーボエ奏者として世界的な活動を始めた。22歳の若さでベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の首席オーボエ奏者に就任。若くして非凡な才能を見せて来た。1970年代、カラヤン/ベルリン・フィルの黄金期に輝いていたスタープレーヤーです。34年間もベルリン・フィルの首席オーボエを務め、カラヤンを支えたひとりでした。「オーボエを吹いているか、ピアノを弾いているか、それともお酒を飲んでいるか」といわれるほどお酒が好きではありますが、本番では神経質であり誠実な演奏者。
- 藤家 虹二(ふじか こうじ) 1933年 ~2011年

広島県出身。日本のジャズクラリネット奏者。 東京藝術大学音楽学部器楽科に首席で入学し、首席で卒業。在学中からジャズに身を投じるが、クラシックでも1956年、毎日音楽コンクール管楽器部門で第1位となった。
ベニー・グッドマンに傾倒し、その後はスウィング・ジャズ一筋に演奏を続けた。1959年に南部三郎クインテットに参加。南部三郎が突如バンドを脱退したため、メンバーで相談の末、藤家がリーダーとなって、同年12月に藤家虹二クインテットとして再出発した。テクニックにモノをいわせ、複雑なフレーズを一糸乱れずプレストのリズムに乗って展開、腕達者のプレイヤーを集め、水準の高い演奏を誇った。その後も長きにわたり「藤家虹二クインテット」を率いてスウィング・ジャズ専門に活躍した。経営の安定度はジャズ界ナンバーワンとも評された。バンド活動以外にも音楽事務所を興し、経営手腕を発揮した。アレンジや歌謡曲、テレビドラマの劇中音楽、校歌などの作曲とともに、音楽教室など幅広い活動を行った。