|
2020年02月09日 田邉 克彦 歓喜の歌って、一体なんだ? シラーからベートーベンへ 1963年11月、日比谷の日生劇場が開場した。その杮落としにカール・ベーム率いるベルリン歌劇場管弦楽団・合唱団が来日、4晩に亘りオペラを上演した。その番外として、ベートーベンの第九交響曲の特別演奏会が7日に開かれた。ニッポン放送の技術者が、それをライブ録音した。当時は未だ劇場録音が珍しかったので、このCD(89年制作)は歴史的名盤といわれた。ベートーベン生誕250年を前に、昨年12月にこのCDが復刻された。 これを聴きながら(時間の関係で、第1及び第4楽章のみ)、改めて第四楽章の「歓喜の歌」とは一体なんだったのかをシラーの原詩と対比しながら、考えてみたい。 シラーの原詩(An die Freude)は1786年、フランス革命直前の王政批判、一般民衆の自由、平等、博愛を求める動きの高まりの中で書かれた。若きシラーが思い切り自らの思いを歌い上げた全九節の長大な詩で、ボン在住のベートーベンが革命実現後の1982年頃にこれを読んで感激、作曲しようと思い立ったといわれる。その断片は、合唱幻想曲など様々な曲に現れているが、完成した形となったのは、晩年の第九交響曲においてである。 合唱を組み込んだ交響曲は、音楽史上これが初めてであり、独特のアレンジがほどこされているため、シラー研究者やベートーベン愛好者からも見逃されている点も多い。それを拾い出して、ベートーベンの真意を明らかにしたい。 シラーの原詩は、9節(各8行の詩と4行の合唱から成り、全体で18の部分に分かれている)の長いもので、特定の男性グループのために書かれたものと思われる。当時の経緯や歌詞からみて、学生同盟(Burschenschaft)かフリーメイソン(Freimaurer)の集会のためだったと思われる。研究者によると、早くからライプチッヒなどで、巷の色々な音楽家によって付曲され、広く歌われていたといわれる。 ベートーベンは、この詩の中から6つの部分(3つの詩と3つの合唱)を選び出し、順序も入れ替えるなどの工夫を施して、最後の第4楽章に組み込んだ。この楽章は、音楽的ドラマの形で進行する。先ず苦悩を表す激しいファンファーレに続き、第1、第2、第3楽章が否定され、中心的テーマとなる歓喜のメロディーがおずおずと現れる。 この主題部分は、順次進行(オペレッタなどで多用される歌い易いもの)で、その展開後には、トルコ行進曲の形が現れ、さらにその後に教会旋律(グレゴリオ聖歌)に変わる。最後は、教会旋律と歓喜の歌の二重フーガとなって全曲を終える。つまり、新勢力となった市民層に馴染みの旋律も繋ぐことによって、彼等に向けた音楽を表現しようとしたものと言えよう。ナポレオン失脚後の反動的な政治体制の中で、改めて共和体制の市民社会の実現を願い、一般民衆を勇気付けようとしたベートーベンの意図が受け取れる。それまでの交響曲が王侯貴族のサロン向けのものだったのに対し、俺の音楽は「開かれた劇場での一般大衆相手のものだ」という宣言である。それは、やがて全世界に広まって行き、今日にまで繋がっており、ベルリンの壁崩壊後のバーンスタインによる大演奏会や、欧州連合(EU)の国歌になったり、佐渡裕の百万人の第九になったり、等々。 但し、当初の評判はあまり芳しいものではなかった(ウィーンでの初演は兎も角、再演は不入りだった)。あまりに長大で、初めての合唱付き交響曲で、シラーの詩も難解だったことなどのため、といわれている。 演奏;ベルリン歌劇場管弦楽団、指揮 カール・ベーム、 演奏時間:第1楽章 16:17 音源:CD キング・インターナショナル KKC2515 参考文献:「シラーの「An die Freude」からベートーベンの「合唱」へ(岩川直子) |
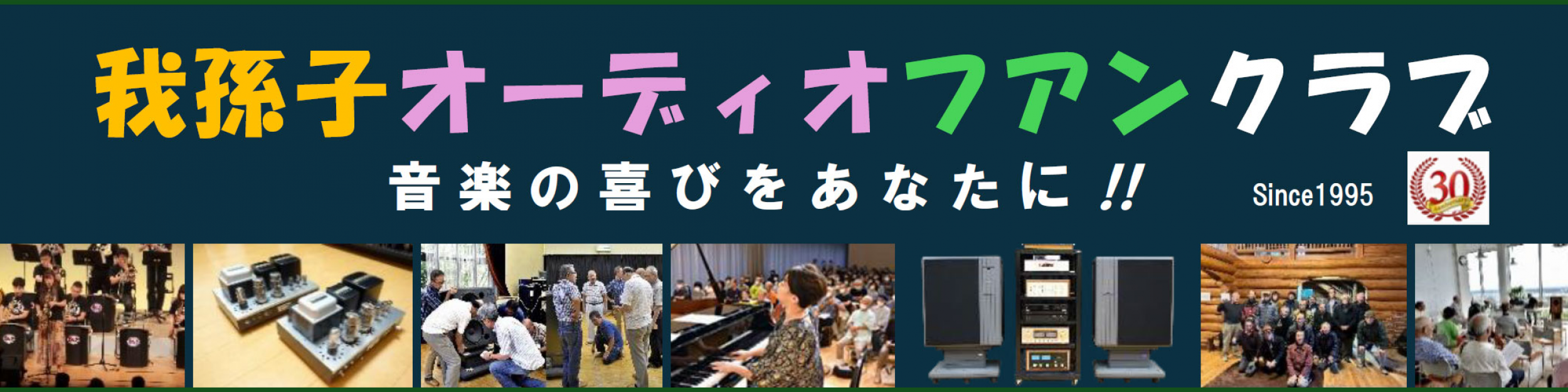

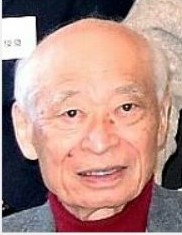 AAFC例会
AAFC例会